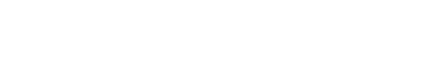国連の窓からジェンダー平等を考える
澤西三貴子 / Sawanishi Mikiko(日本)
国連民主主義基金(UNDEF) 次長 / 2018年度ALFPフェロー
ニューヨークの国連機関に勤務している邦人職員は圧倒的に女性が多い。名簿に掲載されている人数だけでも約200人のうち、女性は約70%を占める。最近の傾向としては邦人の幹部職員(D1レベル以上)のうち女性の占める割合も多くなっている。国連システム全体において、職員に占める女性の割合、特に専門職以上、その中でも幹部職員に占める割合を高めようというのは事務総長の優先事項の一つである。1 もともと国連職員は、専門職と一般職に職種が分かれており、後者は前者の補佐的な仕事を任されるのであるが圧倒的に女性が多い。専門職については、エントリーレベル(P1及びP2)のポジションは女性の方が多い。また最近、事務総長の肝入りで、事務局事務次長や関連機関トップのポストは男女比率の均衡が図られたが、問題は、組織の中核となって仕事をする中堅・幹部を男性が多く占めていることだ。明らかなガラスの天井がある。
男女の機会均等、女性の地位向上は国連が長年取り組んできた課題である。1946年には女性の地位委員会が発足し、1979年には女子差別撤廃条約が採択された。その後1985年に日本が条約を批准したことによって、多くの差別的取り扱いが改善された。私はその頃学生だったが、それまで男性に限られていた就職面接の門戸が女性にも開かれるのを見て、国連というと遠い存在に感じていたが、こうやって直接私の人生に影響を与えることがあるのだなと思ったのが、私と国連の出会いだったのかもしれない。その後も国連は女性の地位向上を推進し、それにより、1999年に女子差別撤廃条約に個人通報制度を可能にする選択議定書が採択されたり、2030年までの持続可能な開発目標(SDGs)にもジェンダー平等は第5の目標として明記されることとなった。
私が仕事で携わっている草の根民主主義の促進においても、ジェンダー平等は全ての事業に要求される視点であり、女性の政治およびあらゆる意思決定への参加が直接的な事業目標として掲げられることも多い。2 プロジェクトの実施機関として対象国の市民社会団体と連携して仕事をしているが、団体の代表も構成員も女性が多く、女性に限らずあらゆる人が意思決定のプロセスに関与できるように、使命感を持って事業に取り組んでいる。

ために、コミュニティでとるべき行動を考えている様子
インドでは、女性が就業できる能力を開発し、経済力に伴って発言力が増し、地域の問題の解決に積極的に取り組んでいる姿を見た。フィリピンやカンボジアでは気候変動やそれに付随する洪水や干ばつなどの自然災害に備えるため、女性がコミュニティ内で予防や被害の拡大を防ぐために何ができるかを積極的に提言し実現していた。マレーシアでは、時代に沿ったイスラム家族法の解釈を提案するために、イスラム女性団体が、度重なる保守派の脅迫にも屈せず、果敢に行動する姿に感動した。アジアのみならず世界中でジェンダー平等を達成する努力が続けられているが、道のりは険しい。性別・性的志向に関わらず個人として自己実現ができ、社会に貢献していく道が開かれなければ、真の民主主義は達成できない。
ジェンダー平等を達成できない原因として、多くの国の活動家が挙げるのは、性的役割分担に関する先入観が固定され変わらないからだという。性別によって、こうあるべきという固定観念から抜け切れず、結果としてその固定観念を前提とした社会制度を構築し、維持することになり、そのことがまた固定観念をより強固なものにしてしまう。父権主義に基づく役割分担観念は、北欧諸国を除けばほぼ全ての国で、程度の差はあれ社会に根強く残っている。他のアジア諸国ではハイレベルの地位につく女性の活躍を目にすることも多いが、反面、男尊女卑の考え方・慣習が多く残っていると、私が仕事で関わるアジアの女性はため息をつく。
日本でも職場や家庭での役割分担の観念が強く、それを前提とした職場慣行や社会制度が構築されてきた。家庭内分業を前提とした長時間労働はその最たるもので、毎日夜遅くまで働いていると家庭を顧みることが難しいし、少子化の原因ともなっている。実は、国連に邦人の女性職員が多いのは、国際社会に貢献したいという強い思いとともに、日本では困難を伴う、職業生活と家庭生活がごく自然に両立できやすいことも一因だと思う。性別役割分担の観念を変化させるためには、女子差別撤廃条約の例のように国際社会における規範形成によるトップダウンアプローチと、家庭や職場での意識改革を達成するための個々人の実践によるボトムアップアプローチの両方が必要となってくる。私たちの娘たちの時代には、性別にとらわれず女性はより活躍できるような社会にもっともっとなってもらいたいと切に願いつつ、少しでもそれに貢献できるように個人レベルでの努力と、多くの女性との連携による集団の力でのたゆみない改革を目指していくしかないと思っている。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。