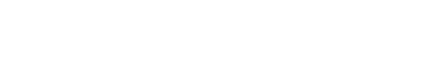情動と論理:音によるコミュニケーション・アート、Randooga
足羽與志子 / Ashiwa Yoshiko(日本)
一橋大学大学院社会学研究科 教授
複雑な世界について言語を使って論じる社会科学にとっては、明瞭簡潔に分析し説明することが重要であり、学者は個別的で情動的な経験を系統化し普遍化する論理という技術を磨くことに腐心する。しかし果たして私たちはどれほどの論理的整合性、合理性の世界に生きているのだろうか。現実は理不尽で矛盾に満ちた情動の世界でもある。暴力や争いも、また共生や和解も、情動の世界に深く根ざす人の心と社会の作用である。しかし情動の社会科学的研究はほぼ未開拓だ。その大きな理由の一つには、情動の世界を言語で論理的に分析し尽くす難しさがあろう。
近年、社会におけるアートの重要性の認識が深まりつつある。しかし情動の世界を深く知るにつけ、社会科学は言葉で論理的に論じることの限界を思い知らされる。私はスリランカの民衆芸能と儀礼の情動の経験世界の調査から文化人類学研究を始め、同国の内戦激化とともに暴力、宗教、アート、政治の問題を研究してきたが、長いスリランカとの付き合いの中でいつも情動が渦巻く現場と社会科学という不完全な論理の檻との間で右往左往してきた感がある。そうしたなかで論理と実践を架橋するためにも、時折、ささやかながらも自らアート関係のイベントを企画した。なかでも印象深いのは、2012年から3年間、スリランカのポスト紛争地の数箇所で実施した、Randoogaという音によるコミュニケーションの企画だった。
2009年に内戦が終結したスリランカは、現在、暴力の記憶を表す現代アートを盛んに生産し、世界のアートシーンで評価を得ている。しかしそうした作品を見るたびに、感心はしたものの、個人的には空虚な思いがぬぐえなかった。作品は名声を得ても、作品は無名の被害者や分断されたコミュニティの日々の生活にいったいどのような救済や和解をもたらすというのだろうか。
研究者として同国の1980年代最初から40年近く紛争の顛末を経験してきたが、進展が見えない闇においても、人々が人々を信じられるモメントがほんの一瞬でもあり、それが重なるならば安心して暮らせる社会の基盤の一部になることを常に痛切に感じていた。とりわけ2009年の武力による内戦終結は「平和」をもたらしても、民族間だけでなく、コミュニティや個人間の内面に深い亀裂を生んだ。紛争の平和的解決に関わっていた内外の人々は、私も含めて、結局は内戦終結が暴力で達成されたという苦い思いと喪失感の中で、何かそれでもできることを探していた。
そんな時に、国際交流基金と在スリランカ日本大使館、現地の大学、内外の音楽家及びNGOの協力のもとに、私が企画する機会を得たのが、Randoogaだった。Randoogaとはフリージャズの先駆者として世界的なジャズピアニストの佐藤允彦氏が、ジャズの即興演奏の概念を使って作り出した、楽器を触ったことがない人も誰でも参加できる、音によるコミュニケーションメソッドである。日本からは他にパーカッションとヴォイスのプロの音楽家、スリランカからはシタールやタブラの奏者が参加し、全国4カ所、述べ4500人以上の参加者と観衆を集めた。参加者は数日のワークショップを経ると、驚くほどの刺激的で喜びに満ちた即興演奏をステージ上でできるようになった。Randoogaの基本ルールは、誰もが楽器や鍋や瓶などの音の出る道具や声を使い自由に短い音を作る、そして互いの音やリズムを聞き、それに自分の音で答える。相手の音にうなずいたり、真似たり、また話を続けたり、切り返したりという音の会話を作っていくのである。自分の小さなフレーズを誰かが聞き留め、それと同じか少し変えたものを返してくれる、それを誰かが聞き、新しいフレーズができる。これは無条件に楽しく嬉しい。上手下手は一切関係ないが、面白いフレーズには複数の賛同がある。でも一人の場の独占が続くとブーイング。そして皆で力と個性を合わせ、全体としてある音の流れを作り出していくのである。

佐藤氏の説明を真剣に受ける参加者
長年の激戦地だった北部のタミルの街、ジャフナでの初めてのRandoogaが最も印象的だった。ワークショップの参加者は最初は半信半疑だったが、シンハラ語かタミル語を母語とし相互に会話ができない人々が、佐藤氏らのリードに従いRandoogaのメソッドを真剣に学び、徐々に音で語り合い始めると、まるで幼友達同士のような愉快な親しみや声をあげての笑いがその場に生まれた。言葉を使わず会話ができる新鮮で純粋な、体の中から湧き上がるような喜びだった。

手拍子と声での対話が始まるとすぐに笑顔
三日後、砲撃で破壊された建物に簡単な修復を施したホールで行った即興演奏会では、音で語り合い受け入れあう喜びが爆発し、観客も演奏者も一体となった。ぜひ映像で見て欲しい。(映像はこちら)

佐藤氏の指示で即興者が交代
修復されたホールでの初めての民間コンサートであり、音楽のコンセプトを超えた即興演奏に、壇上の演奏者も観衆も湧きに湧いた。中学生と一緒に来た校長やシスターも体を大きく揺らしてリズムを取っていた。内戦で苦しみ抜き、未だに苦しむ人々が輝く顔を見せた、奇跡のようなRandoogaのワークショップとコンサートだった。瞬間の出来事だったが、人々は心の底から熱くなり、コミュニケーションできたという信頼と自信と感動があった。
さて問題はその先である。コンサートが終わるとユニセフのスリランカ担当部長が駆け寄ってきてこう言った。「これは世界的に展開できるプログラムだ。メソッドを確立し世界に広めるべきだ」。ジャフナのNGOや音楽の教師からも「あなた方が去った後、続けてやりたいから」と、同様にメソッドの精緻なテキスト化を求められた。ワークショップ用にシンハラ語、タミル語、英語の簡単なテキストは配布していたが、誰もがそれを読めばすぐにRandoogaができる、というシステムとメソッドのテキストは佐藤氏自身も作っていなかった。Randoogaはジャズの即興のように一回性のアートであり、何よりも、佐藤允彦という類い稀な才能のリードのもとに、当時のジャフナの人々の対話と自尊心回復への渇望、スリランカ馴染みのシタールや現地の楽器が参加した親しみや、素人の隣人がステージで変わった音を出す可笑し味、また現地状況をよく知るファシリテーターの大活躍や国際交流基金からの財源、日本大使館支援という政治的安心感や日本や海外のミュージシャンという異人効果、また仮修復だがジャフナの人々の音楽の中核だったホールでの演奏など複数の条件や状況が重なって産み出された一回限りのRandoogaであった。
何が起きるかわからないその即興性に流れるエネルギーと情動こそがRandoogaの本質である。この特徴を知り尽くした佐藤氏も、Randoogaの完全な論理的テキスト化は難しいという。情動の理論化と情動を産みだすこととは別次元の問題であり、分析し論理化してもテキストではRandoogaのエネルギーは説明しきれず、またつくりだせない。情動と論理の問題は社会科学だけではなく、ここにもある。しかしながら、言葉によらないRandoogaのようなコミュニケーションメソッドはまさに現代の分断が進む世界で多くの人々が必要とする。もう一度自分たちでRandoogaをやりたいという人々のためにも、言葉によるロジカルな説明は尽くすしかないのだろう。社会科学による情動分析よりもはるかに難しいが、挑戦には意義がある。現代アートの専門家にも、そのスキルを使い、無名の人々の現実の苦痛を和らげ、分断に和解をもたらす方法が必ずあることを忘れて欲しくない。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。