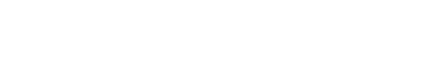文化は人類共通の遺産
サムラート・チョードリー / Samrat Choudhury 1(インド)
作家 / フリージャーナリスト / 2018年度ALFPフェロー
人を「われわれ」と「彼ら」、つまり「内」と「外」とにグループ分けをするのは極めて人間的な性向かもしれない。肌の色など、違いが一目瞭然の場合には、内と外の分別は極めて容易である。だが、違いがそれほど明白ではない時もある。例えば、通りを歩いているインド人、パキスタン人、バングラデシュ人は、当人たちにもなかなか見分けがつきづらい。しかし、それによって、バングラデシュ移民と思われる人々を追い出そうとするインドのヒンドゥー民族主義者たちの気勢が削がれることはない。むしろ彼らは、何百万ものバングラデシュ人が知らないうちにインドに入り込んでいることに不安を覚える。この不安の根底にあるのは権力の問題だ。民主主義には、大多数を占める集団が権力を掌握してしまう危険性がある。ヒンドゥー民族主義者たちは、バングラデシュからのイスラム系移民の増加によって、自分たちの手から権力が奪い取られることを恐れているのだ。この問題をさらに複雑にしているのが、インドの民族的、言語的多様性だ。バングラデシュとの国境付近には少数民族の小さなコミュニティがあり、その多くがキリスト教徒の共同体だが、彼らはヒンドゥー教徒による宗教政治を快く思っていない。しかし、ヒンドゥー民族主義者同様、地域の権力をイスラム教徒たちに奪われることに不安を抱いている。かくして文化とアイデンティティは、国家レベルでも、地域レベルでも、主として権力をめぐる政治的争いの舞台となる。
私たちが生きている世界の現実を考えると、こうした争いは不可避である。機械による輸送手段が発明される以前の世界では、人々はそれぞれの地域社会の中で、外の世界の出来事にほとんど煩わされることなく生活することができた。人々の移動はいつの時代も世界中で起きてきたが、その速度や頻度や規模は極めて限られたものだった。さらに、領土の境界もアイデンティティの境界も流動的だった。世界の大部分では、普通教育が誕生する前のアイデンティティの有りようは、今とは大きく異なっていたと思われる。例えば、言語的アイデンティティは、多くの地域で最も重要なものではなかったようだ。そうした傾向は帝国主義の時代が終わりを迎える第一次世界大戦終結頃まで続いた。この点がよくわかるのが、イギリス王室のアイデンティティの変容だ。イギリス王室はもとはドイツの出身だが、第一次世界大戦の開戦後まで、家名をサクス=コバーグ=ゴータ家からウィンザー家に改めることはしなかった。それまでのイギリス皇帝は、インド女帝も兼ねたヴィクトリア女王(1819~1901年)を含め、何代にもわたってドイツ語を第一言語としていた。ヴィクトリア女王の夫、アルバート公もドイツ人であった。大英帝国の統治者でありながらドイツ語話者という彼らの言語的アイデンティティは、1800年代の言語ナショナリズムの出現までは問題にならなかった。イギリス王室のように、住む土地に合わせて言語的アイデンティティを獲得した例は、世界中に数多くある。私たちは時に忘れがちだが、言語は学習によって会得できるし、長い歴史の中では家名が変わることもままあった。現アメリカ大統領のトランプ(Trump)という姓も、もとはドイツ系のドランフ(Drumpf)だったが、17世紀に先祖が現在のトランプという姓に変えたのだ。さらにドナルド・トランプ大統領の祖父フリードリッヒ(Friedrich)は、ニューヨークに移住した際に名をフレデリック(Frederick)に変えている。2
言語的アイデンティティが勢いを強めてきたのは、一般の言語学習と並行して勃興してきた土着言語の国語化の結果である。ベネディクト・アンダーソンによれば、それは「出版資本主義の市場においてすでに降格させられていた、ラテン語、古代ギリシャ語、ヘブライ語という聖なる古典言語が、雑多な民衆の言葉であった俗語と同列に置かれるまでとなり、平等な立場で覇を競い合わねばならなくなる」過程であった。3 そしてその上に世俗教育制度が打ち建てられたのである。アンダーソンは、エリック・ホブズボームの「学校と大学の進歩はナショナリズムの進展の尺度である。学校、殊に大学は、ナショナリズムの最も意識的な精華である」という定言を引用し、ホブズボームの考えに重要性を加えている。さらに、地図、人口調査、博物館といった3つの制度が、世界の新たな解釈を人々に与えたのである。4 ドイツ系の女王が大英帝国を統べ、遠隔の地であるインドの臣民の忠誠心を概ね勝ち得ることができる世界は消滅した。第一次世界大戦終結から第二次世界大戦勃発までの期間には、オーストリア=ハンガリー帝国やオスマン帝国といった多民族帝国による旧世界が崩壊し、国民的文化と国語を備えた国家による新世界が誕生した。この過程は、第二次世界大戦に続く植民地主義の終焉につながる重要なポイントと言えるかもしれない。
しかしながら、第二次世界大戦は、植民地獲得の野望を抱く新興の帝国主義的国民国家と、すでに植民地を持つ既存の帝国との衝突でもあった。その恐るべき惨禍は、ナショナリズムが帝国主義や植民地主義と結びつくことの危険性を浮き彫りにした。以来、世界は、現実はともかくとして、理屈の上ではこれらの主義から大きく距離を置いている。宗教は、近代国家が誕生した時代にすでに世界の大部分で世俗主義によって隅に追いやられていた。冷戦後には、疑似宗教たるイデオロギーも廃れていった。全てにあてはまる理論はなくなり、人々の心には空洞が生じた。各国のアイデンティティ政治には明らかな経済的側面と政治競争的側面が見て取れるが、より根本的な問題も絡んでいるのではないか。今日私たちが世界中で目にしている、右翼的なリーダーたちへの圧倒的な支持や、宗教的ナショナリズムの台頭といった現象は、消費資本主義が与えてくれるもの以上に安定的で意義深いアイデンティティを人々が求めていることの表れかもしれない。
文化とアイデンティティは人間によってつくられたもので、絶えず変化する傾向にあるが、「自分は何者か」という根源的、実存的問いを考える上で必要不可欠な精神的ソフトウェアになっている。人間が文化とアイデンティティの基盤なしで生きていくのは実質的に不可能である。私たちと、私たちが偶然生まれ落ちた国の国民的、宗教的文化との関係は、しばしば「歴史の天使」と「歴史の悪魔」によって複雑化される。それでもなお、私たちは一つの文化とアイデンティティを捨てようとすれば、別の文化とアイデンティティを身につけないかぎり、生きていくことは到底できない存在だ。

(インド・アッサム州)5
人類の文化の多様性を、生物多様性になぞらえてみたとき、私たちは文化的アイデンティティという厄介な問題との向き合い方について、全く違った考え方にたどり着くのではなかろうか。探検家で人類学者のウェイド・デイヴィスによる有名な言葉は、そのことを非常に巧みに表現している。「他の文化は、あなたのようになろうとして失敗したものではない。人間の精神を独自に具現化したものである」。多種多様な文化は、私たちが生まれた土地の文化を含め、何世紀にもわたる人間の努力と創造性の賜物として、世界のさまざまな地域に育ち、開花したものである。自分の文化だけでなく、すべての文化が、それにふさわしい敬意と愛情を以て遇されるべきであるのは、至極当然のことである。それぞれの文化は人類共通の遺産であり、人間精神の顕現なのだから。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。